営業とマーケがかみ合わない理由は「指標」のすれ違いにある
営業とマーケティングの連携がうまくいかない──。
BtoBの現場でよく聞かれる課題ですが、その原因の多くは「コミュニケーション不足」や「温度感の違い」といった表面的なものではなく、使っている“指標”のすれ違いにあるケースが少なくありません。
たとえば、マーケティング担当者が「CVが増えました!」と報告しても、営業サイドからすると「それって売れる話なの?」とピンと来ない。
逆に、営業が「今月の商談数が足りない」と言っても、マーケ側は「今期はリード数達成してます」と返すだけで、議論がかみ合わない──そんな光景に心当たりはないでしょうか?
指標がずれていると、成果の会話ができなくなる
このようなすれ違いは、単なる“言葉の定義の違い”にとどまりません。
「どの指標を重視しているか」が違うことで、そもそも成果の会話が成立しないという問題に直結します。
- マーケティングは「CV」「MQL」「CPA」などのマーケ指標を軸に成果を測ろうとする
- 営業は「商談数」「受注率」「売上金額」などの営業指標で成果を判断している
お互いに“違うモノサシ”を使って評価しているため、同じ活動を見ていても意味づけがまったく変わってしまうのです。
「売上貢献」という共通ゴールに立ち戻る
このギャップを埋めるには、「売上」という共通のゴールから逆算して、指標を橋渡しする視点が必要です。
たとえば「CVが増えた」と聞いたときに、「そのCVがどれくらい商談につながったか」「その後の受注率は?」という問いが自然に出てくるかどうかで、連携の深さは大きく変わります。
逆に、営業側も「今月商談が少ない」と言うだけでなく、「上流のCVやリード獲得状況は?」と問い返せれば、問題の所在を一緒に特定できるようになります。
最終的に営業の売上を後押しすることこそが、マーケティングの存在意義だと考えています。マーケティング施策の企画・実行・効果検証の各フェーズでは定期的に売り上げへの交換について振り返る時間を設けましょう。
営業でも腹落ちする!マーケティング指標の読み解き方
マーケティングには「CV」「リード」「MQL・SQL」「CPA・ROAS」など、聞き慣れない略語が多く登場します。
しかし、それぞれの指標には営業にとっても実は重要な意味があります。
ここでは、営業視点で腹落ちしやすいよう、代表的なマーケティング指標を売れる文脈で解説していきます。
CV(コンバージョン)=商談数じゃない?本当の意味と活かし方
CV(コンバージョン)とは、ユーザーに取ってほしい行動が実際に行われた回数を指します。
BtoBの場合、代表的なCVは「資料請求」「お問い合わせ」「無料相談予約」など。
この数字が増えると、一見「見込み客が増えた」と思われがちですが、実際にはそのまま商談に直結するとは限りません。
たとえば、SEO経由で集まった資料請求は、営業にとって温度感が低く、追客してもアポが取れないこともあります。
つまり、CVが増えていても「商談につながるCVかどうか」を見極めないと、営業リソースが空回りしてしまうのです。
営業視点で見るポイント
- CVの質(=商談化率)を見る
- どのチャネル経由のCVが受注に寄与しているかを把握する
例:「ウェビナー経由のCVは商談化率30%、オーガニック検索経由は10%だった」
→ どのチャネルに注力すべきか、営業とも会話がしやすくなります。
リード(見込み顧客)にも温度がある?MQL・SQLの違いとは
マーケティングでは、獲得した見込み顧客を「リード」と呼びますが、リードにも“営業しやすさ”の温度差があります。
それを示すのが「MQL(Marketing Qualified Lead)」と「SQL(Sales Qualified Lead)」という考え方です。
- MQL:マーケが「営業に渡してもいいかも」と判断した段階
- SQL:営業が「商談になりそうだ」と判断した段階
MQLの段階では、まだ検討初期の顧客も多く、プッシュしすぎると離脱のリスクも。
一方でSQLは、具体的なニーズや課題が見えはじめた状態なので、営業が動くべき“勝負どき”です。
営業視点で見るポイント
- MQLからSQLへの移行率=営業の初動の質
- MQLの定義が現場とズレていないかを定期的にすり合わせる
社内で「このリードってSQLだったの?」というやりとりが頻発する場合、
そもそもMQL・SQLの定義が曖昧か、共有されていない可能性があります。
CPAやROASは「費用対効果」じゃない?営業的にどう見る?
CPA(Cost Per Acquisition)やROAS(Return On Advertising Spend)は、広告施策の効果を見る指標として使われます。
- CPA=1件のCVを獲得するためにかかった広告費
- ROAS=広告費1円に対してどれだけの売上があったか
マーケ的には「CPAが下がった、ROASが上がった」と聞くと“成果が出ている”と判断しがちですが、営業からすれば「で、そのCVは売れるの?」という疑問が残りますよね。
営業的な視点で考えるなら、「低CPAのCVが実際に受注につながったのか?」、
あるいは「ROASの数字に再販や契約継続も含まれているのか?」など、もう一歩踏み込んで評価する必要があります。
営業視点で見るポイント
- CPAの低さよりも受注単価やLTV(顧客生涯価値)とのバランスに注目
- ROASの計算に営業フェーズ以降の成果(受注や継続契約)が含まれているかを確認
PV・UUって営業に関係あるの?興味関心の“熱量”として捉える
PV(ページビュー)やUU(ユニークユーザー)は、Webサイトへのアクセス数を示す指標です。
営業からすれば「PVが増えても売上には関係ない」と感じがちですが、興味・関心の“熱量”を測る手がかりとして活用できます。
たとえば、ある製品ページのPVが継続的に増えているなら、市場のニーズや注目が高まっている兆しと見ることができます。
また、アクセスが多いコンテンツを営業が把握しておけば、顧客との商談や提案に活かせるヒントにもなります。
営業視点で見るポイント
- アクセスの多いページ=今、関心を集めているテーマ
- 商談中の企業が閲覧していたページがわかれば、ニーズ把握に活用できる
マーケティング関連ツールの多くでは、閲覧ログを営業と共有できる仕組みもあります。
「資料DLの後、どのページを何回見たか」などを追えると、ホットリードの見極めが可能です。
「指標」がわかると、マーケ施策と営業活動がつながる
マーケティング指標の意味が腹落ちしてくると、営業活動との“接続点”も見えやすくなってきます。
ここでは、マーケ施策と営業活動がどう連動しているのかを、営業出身の方にも分かりやすい形でイメージできるよう整理します。
リード獲得から受注までの分業イメージ
BtoBにおけるマーケティングと営業の関係は、単純に“前工程と後工程”というよりも、一連の購買プロセスを分担している関係と捉えるのが実態に近いでしょう。
- マーケ:リードを集め、ナーチャリングして“育てる”
- インサイドセールス(または営業):育ったリードを選別し、商談化を目指す
- フィールドセールス:商談を進めて受注に導く
つまり、各部門が同じ指標の異なるフェーズを担っているとも言えます。
「CV数」→「MQL」→「SQL」→「商談化」→「受注」という流れの中で、
どのフェーズで課題が生じているかを把握できれば、連携の質が劇的に改善されます。
たとえば「SQLは多いのに受注率が低い」なら、提案の質や見込み違いを疑う必要がありますし、
「CV数は多いがMQLが少ない」なら、リードの質や育成プロセスの改善が求められます。
営業にとっての「良いマーケ施策」とは
営業にとっての「良いマーケティング施策」とは、“売れそうな相手”を、営業が動きやすい形で引き渡してくれるものです。
たとえば以下のような施策は、営業現場から高く評価される傾向があります。
- 問い合わせ時点で導入検討の意向が明確にあるリードの獲得
- 過去に接点があったリードを再掘り起こすリテンション施策
- 個社別の閲覧行動データをもとに提案材料を共有してくれるコンテンツ連携
こうした施策は、CVやPVといった“表層的な数字”だけでなく、その後の営業アクションにつながる質的なアウトプットを生み出しています。
マーケ施策が営業に貢献しているかを測るには
- SQL化率(MQL→SQL転換率)
- 商談化率(CV→商談の比率)
- 受注貢献率(全受注のうちマーケ経由の件数や金額)
などの中間指標でのチェックが効果的です。
「何に期待するか」を決めることが、社内連携の第一歩
マーケと営業が連携するうえで意外と重要なのが、「お互いに何を期待しているか」を明確にしておくことです。
たとえば、マーケ側は「商談につながるCVを渡したつもり」でも、営業側が「資料請求は温度が低い」と判断してスルーしてしまえば、せっかくの施策も意味を成しません。
そうしたギャップを防ぐためには、以下のような期待値のすり合わせが欠かせません。
- 「CVのうち●%がMQLになる見込み」
- 「MQL定義はこの条件を満たすもの」
- 「SQLには●営業日以内にアプローチを実施する」
このように、“期待と定義”をあらかじめ共有しておくことが、摩擦のない連携を支える土台になります。
これはKPIの設計ともつながります。部門ごとの目標がバラバラだと、連携しづらくなるため、
「受注から逆算した共通KPI」を設けることも有効です。
営業出身者こそ強い!指標を活かしたマーケ思考のススメ
「営業とマーケは分業」とよく言われますが、現場で成果を出している企業では、営業経験を活かしたマーケティング人材が活躍しているケースが目立ちます。
なぜなら、営業出身者は「売れる兆し」や「顧客の温度感」への感度が高く、指標を数字以上の意味として読み解く力があるからです。
営業経験は、マーケ指標の「意味づけ」に強い
たとえば、CV数の増減を見たときに、単に「施策の効果」としてではなく、
「このCVは営業が追いたいと思える内容か?」「受注につながりそうな興味を持っているか?」といった、実践的な視点で指標を評価できるのが営業経験者の強みです。
また、「このリードはSQLだろうか? それとも育成が必要なMQLなのか?」といった判断を、
商談経験に基づいた肌感覚で行えるため、社内の“指標の精度”そのものを高めていく役割も担えます。
マーケ思考とは「売れる仕組み」をデザインする力
営業が得意とするのは、目の前の顧客と向き合い、その場でニーズを掘り起こし、信頼を築いてクロージングする力。
一方、マーケティングが得意とするのは、「どうすれば“売れる確率が高い状態”を大量に生み出せるか」という再現性の設計力です。
つまり、マーケ思考とは単に数字を追うことではなく、営業が動きやすい“仕組み”をつくる力とも言えるのです。
営業出身者がこの視点を持つことで、
- 顧客像に沿ったコンテンツ施策を考える
- 本当に売れるリードの定義を明確化する
- 営業フローに組み込みやすい仕組みをつくる
といった「現場と戦略の橋渡し役」として、大きな価値を発揮できるようになります。
売上に貢献できる“現場感あるマーケ人材”へ
マーケティングは“なんとなく指標を良くする仕事”ではなく、営業とともに売上をつくる仕事です。
営業経験を活かせば、机上のKPI管理にとどまらず、「この数字の先にいる顧客」の行動や感情を想像しながら指標を扱えるようになります。
結果として、「売上につながるマーケ施策とは何か?」「営業が本当に欲しいリードとは?」といった問いに、リアリティのある答えを出せるようになり、社内でも重宝される“売上貢献型マーケ人材”に近づけるはずです。
営業の売上を最大化する仕組みづくりこそ、マーケティングの本質的な役割です。
営業経験を活かした“売れるマーケ”の視点を、ぜひ社内連携に役立ててみてください。
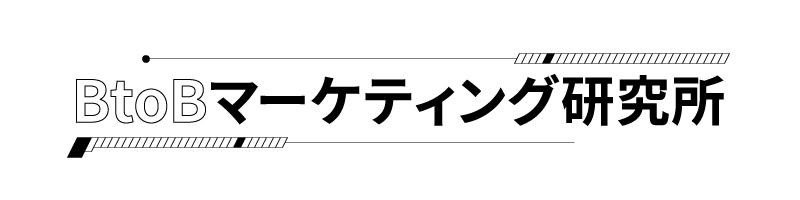


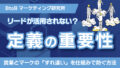
コメント