なぜ今「広告に頼らないリード獲得」が注目されているのか?
中小企業が直面する広告施策の課題
これまで多くの企業が見込み客獲得の手段として利用してきた広告施策。しかし最近では、「広告を出しても思ったように成果が出ない」「費用対効果が合わない」と感じている中小企業が増えています。
特に中小企業にとって、広告予算は決して潤沢とはいえません。加えて、広告単価の上昇や競合の激化により、少ない予算で成果を出す難易度は年々上がっています。たとえばGoogle広告やSNS広告では、クリック単価が高騰し、1件の問い合わせ獲得に数千円〜数万円かかるケースも少なくありません。
加えて、広告によって得られるリードが「温度感が低い」「比較段階にすら至っていない」といった課題もあります。つまり、広告によるリード獲得は短期的には母数を稼げても、商談化や受注にはつながりにくいという現実もあるのです。
こうした背景から、多くの中小企業が「広告だけに頼らず、より本質的な接点づくりを行いたい」と考えるようになっています。
広告に頼らない=成果が出ない、ではない
「広告を使わない=集客できない」と思われがちですが、実際にはそうとは限りません。近年では、広告に頼らずともリードを獲得できる手段が多数登場しており、それらは中小企業のような限られたリソースでも実行可能なものも多く存在します。
たとえば、検索流入を活用したコンテンツマーケティング、名刺交換が可能な展示会出展、既存リストを活用したメールマーケティングなどは、「今すぐ広告費を投じなくても始められる」リード獲得施策として注目を集めています。
さらに、こうした手法は単なるリード数の増加だけでなく、「検討意欲の高い見込み客」との接点構築に寄与する点も見逃せません。広告とは異なる手段を選ぶことで、より“質の高いリード”を継続的に確保する道筋が見えてくるのです。
本質的なリード獲得とは、「マーケティング施策が営業活動を後押しし、売上に直結する状態をつくること」です。広告以外のアプローチは、その可能性を広げる手段のひとつといえるでしょう。
広告に頼らずリードを増やす!中小企業向け7つの施策
① コンテンツマーケティング(SEO記事・ホワイトペーパー)
自社の知見やノウハウを活かし、検索流入を狙った記事コンテンツやホワイトペーパーを提供する方法は、継続的に「関心度の高い見込み客」と接点を持てる有効な施策です。
たとえば、SEOを意識した記事では「○○とは?」「○○の選び方」といった情報ニーズに応えることで、検討段階のユーザーを自然と集められます。さらに、ホワイトペーパーや事例集を用意すれば、資料ダウンロードをフックにリード情報を取得できます。
向いている企業
- 業界に関する知見やノウハウを多く持っている企業
- 定期的に情報発信できるリソースがある企業
実施時の注意点
- 立ち上げ初期は成果が出るまでに数ヶ月かかる
- 「誰に何を届けるか」の設計が甘いと効果が出にくい
外部調査データ
2023年にHubSpotが発表した調査によると、BtoB企業の71%が「コンテンツマーケティングでリードを獲得している」と回答しており、そのうちの多くが「広告よりも費用対効果が高い」と評価しています。
参考:HubSpot|2023年 State of Marketing Report(英語)
② 展示会・リアルイベントでの名刺獲得
オンライン化が進んだとはいえ、リアルな場での出会いには強い訴求力があります。展示会や業界イベントでは、出展者としてブースを構えたり、セミナー登壇したりすることで、自社に興味を持ってくれた来場者と直接名刺交換が可能です。
特に中小企業にとっては、「地域密着」「ニッチ市場での認知拡大」などの文脈で相性がよく、短期的にリードを獲得しやすい施策といえます。
向いている企業
- 営業担当が対面での会話に強みを持っている
- 新規市場・新製品の周知を一気に図りたいと考えている
実施時の注意点
- 出展コスト(数十万〜)や準備工数がかかる
- フォロー体制を整えないと「名刺の山」で終わるリスクあり
外部調査データ
日本能率協会が発表した調査によると、展示会に出展した企業の約68%が「新規リード獲得に成功した」と回答。さらにそのうちの半数以上が、イベント後に商談化していると報告しています。
参考:日本能率協会「展示会活用実態調査2023」
③ ウェビナー(オンラインセミナー)活用
コロナ禍以降で急速に浸透したウェビナーは、コストを抑えつつ、深い情報提供を通じて関心度の高い見込み客とつながれる施策です。
無料セミナーを開催し、参加登録者からリード情報を取得するスタイルが一般的。質の高いテーマ・講師を設定することで、ニーズの強い層との接点を築けます。
向いている企業
- 特定テーマで専門性のある知見を提供できる
- 営業やCSメンバーにプレゼン力・話す力がある
実施時の注意点
- 集客には他施策(メール告知やSNS連携など)との連携が必要
- アーカイブ配信や参加者フォローが成功のカギになる
外部調査データ
Sansanが実施した2022年の調査によると、BtoB企業の60%以上が「ウェビナーで商談機会を創出できた」と回答しており、費用対効果が高い手段として注目されています。
参考:Sansan調査リリース「ウェビナーの実態」
④ 自社サイトの改善(問い合わせ導線・CTA設計)
意外と見落とされがちですが、自社のWebサイトは「最も低コストで改善できるリード獲得装置」です。広告に頼らずリードを増やしたいなら、まず取り組むべきはサイトの見直しです。
たとえば、以下のような改善はすぐにでも実行可能です:
- 資料請求・問い合わせボタンの位置や文言の最適化
- トップページやサービスページの導線改善
- 導入事例・FAQ・料金ページの充実化
また、ブログ記事やホワイトペーパーとの連携も強力です。「次に何をしてほしいか」を明示するCTA(コール・トゥ・アクション)設計により、ユーザーの行動を後押しできます。
向いている企業
- すでにWebサイトを運用しているが成果が出ていない
- インバウンド集客の土台を整えたいと考えている
実施時の注意点
- 社内にWeb担当がいないと改善が属人化しがち
- 改善のインパクト測定には簡単なアクセス解析も必要
外部調査データ
Nielsen Norman Groupの調査では、訪問者の約70%が「目的の情報にすぐたどり着けないとサイトを離脱する」と回答。CTAや導線の設計が、リード獲得に直結する重要要素であることが示されています。
参考:NNG|Website Usability Statistics 2023(英語)
⑤ メールマーケティング(既存接点のナーチャリング)
広告よりもコストをかけずに、「すでに接点のある見込み客」と継続的につながる手段として、メールマーケティングは非常に有効です。
一度問い合わせや資料請求したユーザーに、定期的なメールで情報を届けることで、検討フェーズの深化や再検討を促せます。また、セミナー告知・新着記事案内・業界ニュースなど、接触頻度を維持する工夫も重要です。
向いている企業
- 過去の展示会・ダウンロードなどでリストが蓄積されている
- 継続的に情報発信できる余力がある
実施時の注意点
- 開封率・クリック率などの分析による改善サイクルが必要
- 無理に営業色が強くなると「解除」されやすい
外部調査データ
Benchmark Emailのデータによると、**BtoB企業におけるメール経由のCV(コンバージョン)率は平均6.7%**と、Web広告やSNSよりも高い数値が出ています。特にナーチャリング目的のメールは商談化率に貢献する傾向が見られます。
参考:Benchmark Email|B2Bマーケティングレポート
⑥ 比較サイト・ポータルサイトへの掲載(選ばれるための情報設計)
「サービスを探しているユーザー」が集まるポータルや比較サイトは、自社への“指名検索”がなくてもリードを得られる接点になります。
中小企業にとっては、「自社だけではリーチできない層」との接点を生み出せる強力な手段です。特に、業種特化型の比較サイトやBtoBサービスに特化した媒体に掲載することで、ニーズに近い層からの問い合わせが期待できます。
向いている企業
- 競合と比較されたうえで「選ばれる理由」が明確なサービスを持っている
- Web集客において自社単独では露出が限られる企業
実施時の注意点
- 掲載ページの情報設計・差別化ポイントの見せ方が重要
- 初期費用や成果報酬型のコストがかかる場合もある
外部調査データ
ITreviewによれば、比較サイト経由で商談につながった企業のうち、約72%が「発注確度が高かった」と回答。意思決定段階のユーザーとの接点になる可能性が高いと言えます。
参考:ITreview|ユーザーの購買行動調査2023
⑦ アウトバウンドコール(温度感の高いリードを選別・獲得)
「広告に頼らない」とはいえ、“待ち”だけでなく“攻め”の姿勢も時には必要です。アウトバウンドコールは、リードリストをもとに電話で接点を持ち、ヒアリングやニーズ喚起を通じて商談につなげる手法です。
中でも有効なのは、過去に資料DLや展示会来場の履歴がある「温度感の高い層」に限定してアプローチする方法。これにより、効率よく商談化の可能性を探ることができます。
向いている企業
- インサイドセールス体制がある、または構築予定
- 過去接点リストを活かして再アプローチしたい企業
実施時の注意点
- 営業スキルやスクリプト設計によって成果が大きく左右される
- 一度断られたリードには慎重な対応が必要
外部調査データ
SALES ROBOTICSの調査によると、過去接点リードへのコールで商談化率が約3.8倍に向上したケースもあり、リードの温度感を見極めて活用する重要性が示されています。
参考:SALES ROBOTICS|インサイドセールスレポート2023
自社に合った施策を選ぶための3つの視点
目的に合った手段を選ぶ(認知/獲得/育成)
どんなに効果が高い施策でも、自社の目的とズレていれば期待した成果は得られません。まず大切なのは、「今、何を達成したいのか?」を明確にすることです。
たとえば、次のように目的によって選ぶべき施策は異なります。
- 認知拡大を狙うなら:展示会・比較サイト・コンテンツマーケティング
- 新規リード獲得を狙うなら:ホワイトペーパー・ウェビナー・ポータル掲載
- 既存リードの育成(ナーチャリング)なら:メールマーケ・アウトバウンドコール
こうした目的分類を踏まえて施策を選べば、「なぜやるのか」がチーム内でも共有しやすくなり、実行の解像度も上がります。
工数・リソースと相談する
いくら効果的な施策でも、社内リソースを大きく超えるものは継続が困難です。特に中小企業の場合、「マーケ専任がいない」「兼務で回している」といったケースも多く、実行可能性の見極めは重要です。
施策ごとに求められるリソース感はおおよそ次のように整理できます:
| 施策 | 工数(目安) | 備考 |
| コンテンツマーケ | 中〜高 | 内製 or 外注体制を整える必要あり |
| 展示会出展 | 高 | 事前準備・当日対応・後追いが必須 |
| ウェビナー | 中 | 集客と内容設計にノウハウが必要 |
| サイト改善 | 低~中 | 小さく始められる、効果は中長期 |
| メールマーケティング | 中 | 継続的な運用体制がカギ |
| 比較サイト | 低~中 | 初期構築さえできれば維持は容易 |
| アウトバウンドコール | 中~高 | 人的リソースと営業スキルが必要 |
こうした比較を踏まえて、「無理なく始められるもの」から着手し、徐々に拡張するのも良い選択肢です。
短期と中長期のバランスを考える
最後に重要なのが、短期成果を狙う施策と、中長期で効いてくる施策をどう組み合わせるかという視点です。
広告に頼らないリード獲得の多くは、「すぐに結果が出る」ものばかりではありません。コンテンツやSEO、メールマーケティングなどは育てるまでに時間がかかる一方で、継続すれば資産になります。
一方で、展示会や比較サイトへの掲載は、比較的短期でリードを生み出しやすいため、「種まき」と「刈り取り」のバランスを意識することがポイントです。
マーケティングは“営業が売れる状態”をつくることが本来の役割です。短期的なリード数の獲得だけでなく、育成や信頼構築といった視点も持ちながら施策を組み立てることで、営業チームとも連動した成果が見込めるでしょう。
まとめ|「広告以外」でも成果は出せる、その第一歩を踏み出そう
本記事では、中小企業が広告に頼らずリードを獲得するための7つの施策をご紹介してきました。
それぞれに特性や向き不向きがあるものの、共通して言えるのは――「広告だけが手段ではない」という現実です。
- 自社の知見を活かす【コンテンツマーケティング】
- 顔が見える関係をつくる【展示会・ウェビナー】
- 接点を育てる【メールマーケ・アウトバウンド】
- 「選ばれる場」に露出する【比較サイト・自社サイト改善】
こうした選択肢を組み合わせ、自社に合った方法を見つけることで、より本質的な“売上につながるリード”を生み出すことが可能になります。
最初から完璧な運用は求めすぎず、まずはひとつでも始めてみること。そこから得られる知見こそが、マーケティングを営業の武器に変えていく第一歩になるはずです。
「自社に合ったリード獲得施策をプロと一緒に考えてみませんか?」
Markebuddyでは、広告に頼らないBtoBマーケ施策の立案・実行支援を行っています。まずは無料相談で、現状のお悩みをお聞かせください。
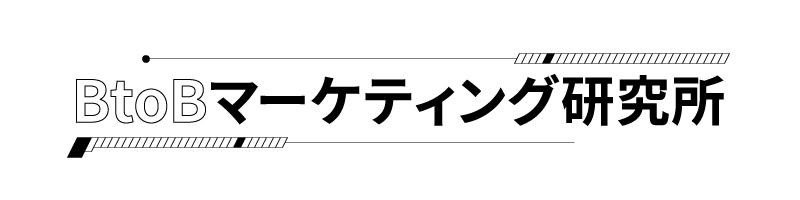

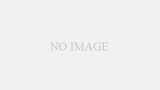

コメント