展示会後に“フォローできていない”中小企業の課題
名刺は集まったのに、営業につながらない理由
展示会で集めた名刺を、なんとなく社内でExcelにまとめて、営業チームに「渡しただけ」になっていませんか?
多くの中小企業では、展示会で得たリード(見込み客)を“その後どう活用すればいいのか”が設計されていないまま、フォローのタイミングを逃してしまうケースが非常に多く見られます。
特によくあるのが以下のような状況です:
- 営業担当が「どの相手に」「どんな順番で」「何を伝えるか」が決まっていない
- マーケ担当は名刺を渡した後の動きに関与しておらず、現場任せになっている
- 一斉メールを送っただけで終わり、個別の対応がなされていない
このような状態では、せっかくの名刺情報も「データはあるのに、案件化しない」という結果になりがちです。
SFAやMAがないから動けない?という勘違い
「SFA(営業支援システム)やMA(マーケティングオートメーション)が入っていないから、フォロー体制がつくれない」と考えていませんか?
実はこれ、ツールがないことが問題なのではなく、「行動設計がされていない」ことが本質的な課題です。
ツールはあくまで“補助輪”であり、設計がない状態で導入しても活用しきれません。
たとえば:
- Excelとスプレッドシートでも、十分な情報整理と進捗管理は可能です
- メールテンプレートやフォロースクリプトを事前に用意するだけで、営業の動きは格段にスムーズになります
- 上司やチームで「誰が・いつ・どうフォローするか」を話し合うだけで、行動が変わります
SFAやMAを「持っていないからできない」ではなく、持っていなくても“できること”から始めることが大事なのです。
最終的に大切なのは、「営業の売上にどう貢献できるか」という視点です。マーケティング部門が“案件化の入り口”まで伴走する意識を持つことで、ツールに頼らなくても成果に近づけます。
SFA未導入でもOK!展示会後の基本アクションフロー
ここでは「ツールがないから何もできない…」という状態を脱して、いますぐ手元のExcelで始められる行動フローを具体的に示していきます。中小企業でも再現可能なステップを、3つに分けて解説します。
1. 名刺情報をまずは「Excelで整理」
展示会で得た名刺は、“ただの名簿”ではなく“営業アプローチの資産”です。まずは以下のような項目をExcelやGoogleスプレッドシートに整理しましょう。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社〇〇 |
| 氏名 | 山田 太郎 |
| 部署・役職 | マーケティング部・課長 |
| メールアドレス | example@company.co.jp |
| 電話番号 | 03-XXXX-XXXX |
| 会話メモ | 「導入事例に興味あり」「次回ウェビナー案内希望」など |
| フォロー予定 | メール送付・電話予定日など |
| ランク | A(導入意欲高)、B(検討余地あり)、C(情報収集レベル)※現場所感ベース |
この「ランク」は、ブース対応者の所感をベースに判断した“温度感メモ”です。
展示会直後の記憶が新しいうちにざっくり分類しておくだけで、後の優先順位付けがぐっとラクになります。
ポイントは、情報を溜め込まずに“動くための管理表”として使うことです。
見やすい色分けやフィルター機能を使えば、SFAのようにリード進捗を可視化できます。
2. 「優先順位づけ」のための3つの基準
名刺を整理したあとは、どの見込み客からアプローチすべきかの“優先度づけが重要です。以下の3つの視点で仕分けましょう。
- 温度感:当日、関心が高そうだったか(導入時期・課題感など)
- 決裁権:担当者か決裁者か?社内に影響力のある立場か?
- 自社との相性:業種・規模・導入余地など、自社サービスとの適合度
たとえば、「導入時期を半年以内と言っていた×部長クラス×既存顧客と似た業界」のような相手は最優先でフォローすべきターゲットです。
このように仕分けするだけで、闇雲にアプローチする時間を大幅に減らせます。
3. 営業や上司と「フォロー分担」のすり合わせ
最後に必要なのは、フォロー業務を属人化させないための“分担と設計”です。Excel上で以下のような項目を追加しましょう:
- 担当者(営業A・マーケBなど)
- 次のアクション日
- ステータス(未対応・メール済・商談化など)
これにより、「誰が」「どのリードに」「いつ動くか」が明確になり、フォローの抜け漏れが防げます。
また、チームで週1回など進捗を共有する時間を設ければ、PDCAが回る状態を手動でも構築できます。
このように、ツールがなくても設計さえすれば「動ける仕組み」はつくれます。
ここでもう一度強調したいのは、フォローの目的は“売上に貢献するため”であるということ。Excelはあくまでそのための“手段”です。
すぐ使える!展示会後フォローのテンプレート例
ここからは、「今すぐ動きたいけど、何を送ればいいかわからない」という方のために、展示会後のフォローで使えるテンプレートを具体的に紹介していきます。
営業・マーケ・資料送付など、代表的な3シーンに分けてお届けします
初回フォローメール(営業向け/マーケ向け)
営業担当からのフォローメール例(Aランク向け)
件名:展示会ではありがとうございました|〇〇株式会社・営業の山田です
本文:
〇〇株式会社 営業担当の山田です。
先日は〇〇展示会の弊社ブースにお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。
短い時間ではありましたが、「●●について興味あり」とおっしゃっていたのが印象的でした。
さっそくにはなりますが、もしご関心があれば、
●●の導入事例などをご案内できればと思いご連絡差し上げました。
オンラインでも構いませんので、一度お話の機会をいただけませんでしょうか?
ご都合のよい日時があれば、ぜひお知らせください。
—
〇〇株式会社
営業部 山田 太郎
mail@example.co.jp / 03-XXXX-XXXX
マーケ担当からのフォローメール例(B〜Cランク向け)
件名:【展示会御礼&資料ご送付】〇〇株式会社です
本文:
〇〇展示会では、弊社ブースにお立ち寄りいただき誠にありがとうございました。
〇〇株式会社のマーケティング部、山田と申します。
当日ご案内させていただいた●●の概要資料をお送りしますので、
ご興味があればぜひご覧くださいませ。
今後、新たな導入事例やオンラインセミナーなども随時ご案内しておりますので、
情報提供をご希望の場合は、下記よりお気軽にご登録いただけます。
▼メルマガ登録フォーム
https://example.com/newsletter
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
フォローメール送信のベストタイミング
展示会後のメールフォローは、“展示会の記憶がまだ残っているうち”に送るのが鉄則です。
特に印象が良かったリード(Aランク相当)には、開催から1〜2営業日以内にメールを送ることで、高い開封率と返信率が期待できます。
一方、会話が浅かったり温度感が低めの方(B〜Cランク相当)に対しては、
展示会後1週間以内を目安に、丁寧なお礼と資料送付を中心にアプローチするのが適切です。
このように、“温度感 × タイミング”の掛け合わせでメール対応を設計すると、
少ない工数でも成果につながりやすくなります。
電話フォローのタイミングとスクリプト
Aランクや「その場で具体的な話をした」リードには、展示会から2〜3営業日以内に電話フォローを入れるのがベストです。
電話スクリプト例(初回コンタクト)
(名刺交換した〇〇展示会の件を切り口に)
「お世話になっております。〇〇展示会でご挨拶させていただいた〇〇株式会社の山田と申します。」
「展示会の際に●●にご興味あると伺いまして、
簡単に事例のご紹介などできればと思いお電話差し上げました。」
(相手の反応を見つつ)
「ご都合いかがでしょうか?5分ほどお時間いただけますか?」
→NGだった場合:「また改めてご連絡させていただきます。ご都合よいタイミングなどあればぜひ教えてください。」
資料送付・お礼メールのテンプレート
メールや電話でのコンタクト後、資料送付やフォロー完了時のお礼メールも重要です。
ちょっとしたひとことが、信頼につながります。
お礼メールテンプレート
件名:【ご案内資料の送付】〇〇株式会社・山田より
本文:
〇〇株式会社の山田です。
本日はお時間いただき、ありがとうございました。
ご案内させていただいた●●の事例資料を添付いたしますので、
お目通しいただければ幸いです。
今後とも、なにかご不明点やご相談などありましたら、お気軽にお知らせくださいませ。
—
(署名)
テンプレートはそのまま使っても、チーム用に少しカスタマイズしてもOKです。
誰がやっても一定の品質でフォローできるように、社内で共有フォルダなどにまとめておくのがおすすめです。
SFAなしでも継続管理する方法と工夫
「最初のフォローはやった。でもその後どうすれば…?」
そんな声は、中小企業の展示会後あるあるです。
ここでは、Excelやスプレッドシートを使って、見込み客との接点を継続的に管理するためのコツをご紹介します。
「仕組み化=高価なツール導入」ではありません。無料ツールでも、運用ルール次第で“簡易SFA”のように機能させることができます。
Excel/スプレッドシートを“簡易SFA”として使う
展示会で整理した名刺データをベースに、以下のようなシンプルな「ステータス管理」の項目を追加することで、
進捗が見える・追える・共有できる管理表を構築できます。
| 項目 | 例 |
|---|---|
| ステータス | 未対応/初回メール済/電話フォロー中/商談化/失注 など |
| 担当者 | 営業A/マーケB など |
| 次のアクション日 | 2025/4/22 など |
| 最終接触日 | 2025/4/15 など |
| 備考 | メール開封あり/先方から反応なし 等 |
色分けやフィルター機能を活用すれば、進捗状況をパッと把握できます。
「連絡忘れ」や「対応かぶり」といった、属人化の落とし穴を防ぐためにも、こうした管理は必須です。
共有と進捗更新のルールを社内で定める
管理表を作っただけでは、情報はすぐに陳腐化します。
重要なのは、「どうやって最新状態を保つか」=運用ルールの設計です。
おすすめは以下のようなシンプルなルール設計です。
- 毎週●曜日にチームで進捗を更新・共有(例:月曜AMに10分ミーティング)
- 更新担当は営業本人、またはマーケが代理で入力
- 商談化・失注したリードは色分け or ステータスで分類
「見える化 → 行動 → 共有 →見直し」のミニPDCAを回すサイクルをつくることが、継続的な成果につながります。
次回展示会に活かすための情報整理法
管理表は、「いま」の商談化だけでなく、次の展示会をもっと成果につなげるための“財産”にもなります。
たとえば以下のような項目を残しておくと、次回のターゲット選定・メッセージ設計・ブース運営に活かせます:
- 業種/規模別に反応が良かったパターン
- どの展示会でどの属性の来場者が多かったか
- 商談化につながった人の会話キーワードや関心事
- 成果につながらなかった理由(担当者レベル/予算感/競合との比較など)
こうした情報は、「展示会で成果を出すチーム」へと成長するためのデータ基盤になります。
SFAを導入しなくても、
“必要な情報を見える化し、共有・更新し続ける仕組み”があれば、営業活動は十分に前に進められます。
逆にいえば、ツールを導入したとしても、この運用設計がないと活かしきれません。
まとめ|ツールがなくても「設計」と「継続」が成果を生む
展示会で集めた名刺は、正しく活用すれば営業成果に直結する“宝の山”です。
ですが、その価値は「どうフォローするか」「どう管理するか」という行動の設計と継続がなければ活きません。
この記事では、SFAやMAといったツールがなくてもできる、基本の行動フローとフォローの考え方をお伝えしてきました。
- Excelでの情報整理・優先順位づけ
- チームでの分担設計と管理ルールの策定
- メール・電話・資料送付といった具体的なテンプレ活用
- 継続管理とナレッジ蓄積による次回施策への活用
いずれも、特別なシステムや予算がなくても始められる内容です。
そして何より大切なのは、
マーケティングの目的は「営業の売上に貢献すること」だという視点を持ち続けること。
「名刺を渡して終わり」ではなく、「どうすれば案件化に近づけるか」を考えながら動ける体制を、少しずつ整えていくことが成果への一歩です。
🟢 「うちでもこの仕組みつくれるかな?」と思ったら、Markebuddyの無料相談をぜひ
- SFAやMAがなくてもできる営業設計を一緒に考えます
- 展示会活用やリード管理の仕組み作りをサポート中!
👉 無料相談はこちら
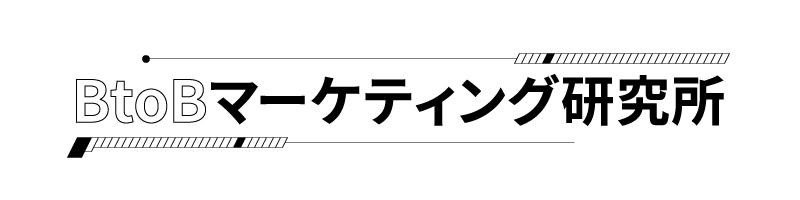

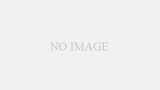
コメント