展示会準備でありがちな「よくある失敗」とは?
はじめて展示会を担当する方にとって、一番の不安は「なにか抜け漏れがあるのでは?」という点ではないでしょうか。
展示会は関係者も多く、準備期間も長期にわたるため、ちょっとした認識ズレや後回しが思わぬトラブルを招くことも少なくありません。
ここでは、特に若手担当者がつまずきやすい3つの失敗パターンを紹介します。事前に知っておくだけで、ぐっと安心して準備に臨めるはずです。
スケジュールが直前すぎる
展示会の準備で最も多い落とし穴が、動き出しの遅さです。
「まずは情報収集から」「営業部に確認してから」と後回しにしているうちに、気づけば本番まで1ヶ月を切っていた…というケースも珍しくありません。
特に注意が必要なのが以下のようなタスクです:
-
出展申込の締切(意外と早い)
-
ブース設計・施工会社との打ち合わせ
-
パンフレット・ノベルティ制作(印刷に時間がかかる)
-
営業部との説明資料共有・事前練習
こうした作業は外部パートナーや他部署が関わるため、自分ひとりで調整できない=スケジュールが読みづらいのが特徴です。
目安としては、展示会の3ヶ月前には準備をスタートしておくと安心です。
営業部門との連携不足
展示会はマーケティング施策の一つではありますが、当日ブースで実際に来場者と対話するのは営業部であるケースが大半です。
しかし、以下のような連携ミスが起こると、本番でのパフォーマンスに大きく影響します:
-
何を目的に出展しているのか、営業側が理解していない
-
話すべき製品や訴求内容が人によってバラバラ
-
そもそもブースに立つ人が誰なのか、共有されていない
展示会を「名刺獲得イベント」で終わらせず、受注に結びつけるマーケ施策とするには、営業部門との密な連携が欠かせません。
当日だけでなく、事前の説明会やロールプレイング機会を設けるのも有効です。
営業との連携がうまくいくと、展示会の“熱量”が商談フェーズまで持続します。
展示会は単なる名刺獲得ではなく、“売上につながるコミュニケーションの場”と捉えることが重要です。
目的や成果指標が曖昧なまま進行
「毎年出ているから今年も出す」というように、目的があいまいなまま準備が進む展示会も少なくありません。
その場合、関係者間で優先順位がずれたり、後から成果の評価がしにくくなる可能性があります。
以下のような軸を、企画初期に必ず明確にしましょう:
-
展示会の目的:認知拡大/新製品PR/リード獲得/既存顧客との関係強化 など
-
成果指標(KPI):名刺獲得枚数、商談件数、SNS反応数、資料DL数など
こうした目的設計を「上司から言われたからやる」のではなく、営業・経営ともすり合わせて合意形成することが大切です。
これがあるだけで、準備の方向性もブレなくなり、振り返りもしやすくなります。
展示会準備〜当日運営の全体像
展示会は“準備がすべて”とも言われるほど、事前の段取りが成否を大きく左右します。
ここでは、展示会当日までの全体スケジュールと、主な準備項目、当日の運営イメージを俯瞰的に把握できる構成で整理しました。
「どこから手をつけたらいいか分からない…」という方は、まずこの流れを全体像として押さえておきましょう。
展示会までの全体スケジュール(3ヶ月前〜当日)
展示会準備は、最低でも3ヶ月前から逆算しておくのが理想です。以下は一般的なスケジュール例です。
| 時期 | 主なタスク |
|---|---|
| 3ヶ月前 | 出展目的・KPI設定/ブース位置・申込確定/営業との方向性すり合わせ |
| 2ヶ月前 | コンテンツ設計(訴求内容・製品選定)/制作物の外注発注(パネル・動画など)/ノベルティ選定 |
| 1ヶ月前 | スタッフアサイン/当日マニュアル作成/交通・宿泊手配/営業説明会 |
| 1〜2週間前 | 搬入出スケジュール共有/当日の役割分担表作成/最終リハーサル |
| 前日〜当日 | 搬入・設営/リーフレット配布・声かけ対応/ブース内の運営管理 |
主な準備項目(コンテンツ・ツール・人員体制)
コンテンツ・訴求内容
-
出展テーマやキャッチコピーの設計
-
展示製品・サービスの選定
-
デモ機や展示資料の用意
-
動画やタブレットなどのデジタル活用
制作物・配布物
-
パネル・ポスターのデザイン・印刷
-
リーフレット、パンフレット
-
ノベルティ(来場者に配布する小物)
オペレーション・体制
-
スタッフ配置(誰が、いつ、どの時間に立つか)
-
声かけフレーズやトークスクリプトの用意
-
名刺管理・商談メモのフォーマット決定
-
来場者の導線設計(受付、商談、退出まで)
展示会当日の流れと現場オペレーション
| 時間帯 | 内容 |
|---|---|
| 開始前(〜9:00) | 搬入・設営/配布物配置/朝礼・最終確認 |
| 午前中(10:00〜) | 声かけ/名刺交換/簡易ヒアリング(スクリプト活用) |
| 昼休憩(12:00〜13:00) | スタッフ交代で昼食・休憩/来場数チェック |
| 午後(13:00〜) | 商談対応/トークの微調整/来場分析メモ |
| 終了後(〜18:00) | 撤収準備/翌日のための振り返り/名刺整理と保管 |
📊参考リンク:
中小企業基盤整備機構「展示会活用ガイド」
https://www.smrj.go.jp/doc/guidebook_exhibition.pdf
【保存版】展示会チェックリスト(PDF付き)
展示会準備には、細かくて見落としやすいタスクが数多く存在します。
だからこそ、チェックリストを使って「今どこまで進んでいて、何が未完なのか」を常に可視化しておくことが、安心して本番を迎えるための鍵になります。
ここでは、「準備段階」「当日運営」「展示会後」の3ステップに分けて、チェックリストの一部をダイジェストでご紹介します。
1. 準備段階のチェックリスト
| チェック項目 | 完了状況 |
|---|---|
| 出展目的とKPIを定めた | ☐ |
| 展示会申込とブース位置確定 | ☐ |
| 訴求内容・出展製品を決定 | ☐ |
| パネル・配布物の制作発注 | ☐ |
| スタッフィングと役割分担決定 | ☐ |
| 営業部門とのすり合わせ完了 | ☐ |
| 当日マニュアル・持ち物リスト作成 | ☐ |
| 名刺管理・記録ツールの準備 | ☐ |
2. 当日運営のチェックリスト
| チェック項目 | 完了状況 |
|---|---|
| 会場入り/搬入・設営完了 | ☐ |
| スタッフ全員がスケジュールを把握 | ☐ |
| ブース内での声かけフレーズ確認 | ☐ |
| 商談・ヒアリングメモ記入ルール共有 | ☐ |
| 配布物/ノベルティの補充体制 | ☐ |
| 名刺整理・即日デジタル管理の体制 | ☐ |
| 問い合わせ対応の担当者明確化 | ☐ |
3. 展示会後の初動チェックリスト
| チェック項目 | 完了状況 |
|---|---|
| 名刺・記録データの整理・共有 | ☐ |
| ホットリードへの即時フォロー | ☐ |
| 来場者へのお礼メール送信 | ☐ |
| 展示会の成果報告(営業・上長向け) | ☐ |
| 反省点・改善案の振り返り会実施 | ☐ |
| メルマガ登録・資料DLなどの導線分析 | ☐ |
チェックリストを活かすための3つのアドバイス
せっかく丁寧に作ったチェックリストも、「使いっぱなし」では効果が半減してしまいます。
展示会はチームプレイで進行するため、チェックリストをいかに“生きたツール”として運用できるかが、準備〜当日〜振り返りすべての質を左右します。
チームで使うなら、進行管理ツールとセットに
紙やExcelのチェックリストも便利ですが、複数人で共有するにはデジタル化が必須です。
おすすめは以下のような進行管理ツールとの併用です:
-
Backlog/Asana/Notionなどのタスク管理ツール
-
Googleスプレッドシート+コメント欄での進捗確認
-
社内チャット(Slackなど)と連携した通知設定
特に若手マーケ担当者の場合、「自分だけで進めるのではなく、周囲と状況を共有しながら調整する」ことが求められます。
役割分担と共有ルールを事前に定めておく
チェックリストの運用でありがちなのが、「誰が何を担当するのか分からない」「気づいたら進んでなかった」という事態。
これを防ぐには、以下のような役割と運用ルールの事前定義が効果的です:
-
各タスクの責任者を明示
-
進捗更新の頻度(例:週1回確認)
-
変更・相談時の連絡フロー(例:Slackで一言)
展示会後の“振り返り会”で改善点を残す
展示会が終わったあと、できるだけ早いタイミングで簡単な振り返り会を開くことを強くおすすめします。
理由はシンプルで、「展示会の学びは、翌年に引き継がれなければ意味がない」からです。
このタイミングでチェックリストもアップデートしておけば、次の展示会で“最新版”として再活用可能になります。
社内のナレッジ共有にもつながり、チーム全体の底上げが図れます。
振り返りの中で、「どの商談が最終的に売上につながったか」まで追えると、展示会のROIが見える化され、次回施策の説得力も増します。
まとめ|展示会成功のカギは「準備8割、当日2割」
展示会は、単なる「イベント対応」ではなく、営業成果につながるマーケティング施策の一つです。
そして、その成功の大部分は、当日ではなく「準備段階」で決まるといっても過言ではありません。
この記事では、よくある準備の失敗パターンから、全体スケジュール、そして活用できるチェックリストまでをご紹介してきました。
展示会準備で意識したいのは、次の3つです:
-
「目的」「KPI」を明確にし、チームで共有すること
-
チェックリストで進行管理し、役割分担と情報共有を徹底すること
-
展示会後の初動・振り返りまで含めて1サイクルと捉えること
特に、展示会後の“お礼メール”や“名刺のフォロー”といった対応が遅れると、せっかくの来場者の関心も薄れてしまいます。
**展示会はゴールではなく、「商談の入り口」**であることを意識して、リード獲得後の動きまで設計しておきましょう。
🟢 Markebuddy無料相談はこちら
展示会をきっかけに、もっと成果につながるマーケティング施策を実現したい方へ。
Markebuddyでは、事前準備〜リード活用までを専門家がサポートします。
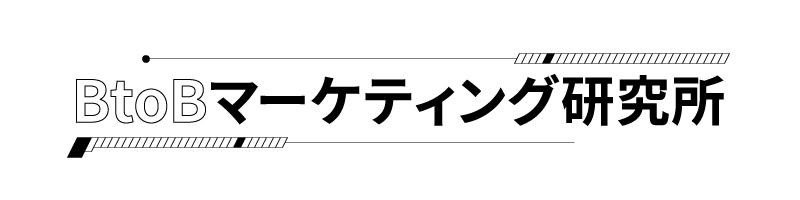

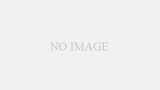
コメント