営業とマーケでよくある「リード定義のズレ」とは?
リード数は多いけど、営業が動かない…なぜ?
「今月も○○件のリードを獲得しました!」
マーケティング担当者がそう報告しても、営業側から「ぜんぜん良い案件じゃない」「動ける状態じゃない」という反応が返ってくる——。
このような“リードのすれ違い”は、BtoBマーケティングの現場で珍しくありません。
なぜこのような状況が起きるのでしょうか?
多くの場合、マーケ側が「有望な見込み顧客」と考えて送ったリードが、営業側にとっては「まだ検討段階にも入っていない」「すぐには商談化しない」と受け止められているケースが多いようです。
リードの“数”は追えていても、双方がその「質」をどう定義しているのかが曖昧なままでは、せっかく獲得したリードも活用しきれません。
「まだ早い」「なんで渡さない」すれ違いの本質
マーケから見れば「そろそろ営業に渡すべき」と判断したリードでも、
営業からすると「まだ温まってない」「情報が足りない」といったギャップが生じることがあります。
逆に、営業から「早くリードをくれ」と催促される場面でも、マーケ側は「まだ育成中」「時期尚早」と判断していることもあるでしょう。
このようなすれ違いの背景には、「リード」という言葉の定義がチームごとに異なっていることが挙げられます。
特に中小企業や少人数体制の組織では、マーケと営業の役割が明確に分かれておらず、“なんとなくの感覚”で判断しているケースが多く見られます。
ここで重要なのは、「どちらが正しいか」を議論するのではなく、
同じ言葉を使っていても指している中身が違うという事実に気づくことです。
このように、“リード活用がうまくいかない”と感じたときには、
まず「自社の中で“リード”という言葉はどう定義されているのか?」を立ち止まって確認することが、
最初の一歩になります。
リード定義の共通言語化がカギ
MQL/SQLとは?営業向けにざっくり解説
BtoBマーケティングにおける「リード活用」を本当に進めたいなら、
まず取り組むべきは「言葉のすり合わせ」です。
中でもよく出てくるのが「MQL(Marketing Qualified Lead)」と「SQL(Sales Qualified Lead)」という言葉です。
MQLは、「マーケティング的に“商談の可能性が高い”と判断されたリード」。
SQLは、「営業的に“商談化に進められる”と判断されたリード」を指します。
少し乱暴に言えば──
- MQLは「そろそろ営業に渡しても良さそうな人」
- SQLは「営業が実際にアプローチして結果が出そうな人」
というイメージです。
この2つをきちんと区別し、営業とマーケが共通認識を持っていないと、
「マーケは良いと思ったのに営業は動かない」「営業に渡したら放置された」といったトラブルの火種になります。
判断基準は“行動”と“情報”の掛け合わせで考える
では、どうやって「MQL/SQL」を判断するのか?
ここで大切なのは、リードの“行動”と“持っている情報の量・質”を掛け合わせて考えることです。
たとえば以下のような判断軸が使われます:
| リードの行動 | 持っている情報 | MQL/SQLの目安 |
|---|---|---|
| 資料を1回だけDL | 氏名・会社名のみ | まだMQLではない |
| セミナーに複数回参加 | 部署・役職・課題感あり | MQLに近い |
| 問い合わせ・個別相談依頼 | 導入時期・予算・意思決定者情報あり | SQL候補 |
単純な行動だけで判断すると「とりあえず資料だけ見た人」も対象になってしまいます。
逆に情報が揃っていても、本人が何もアクションを起こしていなければ温度感が読めません。
そのため、両者をセットで見て総合的に判断するルールが必要です。
属人的な判断を避ける「受け渡し基準」の設計例
とはいえ、「毎回個別に判断する」のでは属人化してしまい、スケーラブルな運用ができません。
そのため、多くの現場では営業に渡すべき“受け渡し基準”をあらかじめ設定しています。
たとえば以下のようなルールが考えられます:
- 受け渡し基準例①:スコア制
- 行動・属性に点数をつけ、合計●点以上で営業に渡す
- 例:「資料DL=5点」「役職が部長以上=10点」「導入時期記載あり=15点」
- 受け渡し基準例②:行動+情報のチェックリスト
- 両方の条件を満たした時点で引き渡し
- 例:「ウェビナー参加済み」+「課題・部署情報あり」
このように基準が明確であれば、
マーケから営業への“引き渡しタイミング”が属人的にならず、トラブルも最小限にできます。
リード活用においてもっとも地味で見落とされがちな「定義の共有」。
しかし、ここを曖昧にしたままでは、どれだけリード数を増やしても“活用できない仕組み”のままです。
「誰の仕事か」ではなく「どのタイミングか」を決める
理想は分業、現実はグラデーション
「リードはマーケの仕事」「営業がもっと活用すべき」——
BtoB企業の現場では、こうした“押しつけ合い”の空気が生まれがちです。
確かに理想を言えば、マーケティングはリードを創出・育成し、営業は商談化・受注に集中する、という明確な分業体制が望ましいでしょう。
しかし、実際にはその境界線がグラデーションになっている企業が大半です。
- リードが獲得されても、営業が「まだ早い」と判断して動かない
- 商談になりそうな相手がいても、情報が足りずマーケに戻される
こうした現象は、「誰の仕事か」が曖昧だからではなく、
“どのタイミングで誰が関わるべきか”が設計されていないことが原因です。
フェーズごとの役割分担モデル(実例付き)
この課題を解決するためには、リードの状態に応じて、どの部署がどう関わるかを段階的に整理することが有効です。
以下はよくある役割分担モデルの例です:
| フェーズ | 主担当 | マーケの役割 | 営業の役割 |
|---|---|---|---|
| 潜在層(興味・関心段階) | マーケ | 情報提供、興味喚起コンテンツ配信 | なし(もしくは反応観察) |
| 顕在層(検討初期) | マーケ中心 | 問題提起型コンテンツ提供、セミナー誘導 | 軽微なフォロー・反応ヒアリング |
| 商談化候補(具体検討) | 営業中心 | 営業支援資料の提供、事前インサイト共有 | アプローチ・ヒアリング・提案 |
| 商談進行〜受注 | 営業 | フォロー資料の供給、カスタマーサクセス連携 | 受注クロージング、継続支援提案 |
このように、フェーズによって“主導権がどちらにあるか”を明確にすることで、
「これは営業が動くべきか?」「マーケで止めておくべきか?」という迷いを減らせます。
共通KPIを持つことで“押しつけ合い”をなくす
もう一つ重要なのが、営業とマーケが“共通のゴール”を持つことです。
たとえば「SQL化件数」や「商談化率」などを共通KPIとすることで、
「とにかく数を渡せばOK」でも「渡されても意味がない」でもなく、
“成果に直結するリードをつくる”という共同責任が生まれます。
この共通KPIがあることで、営業とマーケは互いの動きを理解し、
協力して“リードを活かす”姿勢に近づいていきます。
リードを活かすには、継続的なすり合わせが必要
定義は変化する前提で“定期見直し”を
リードの定義や、営業・マーケそれぞれの役割分担は、
一度決めたら終わりではありません。
- 事業戦略の変化
- ターゲット市場の見直し
- インサイドセールスやカスタマーサクセスなどの新体制導入
こうした変化があるたびに、「今の定義や基準は適切か?」を見直すことが必要です。
特に、BtoBマーケティングにおけるリード活用は、
「どの層をMQLとするか」「SQLの基準はどうするか」など、事業フェーズごとに変わる前提で考えるべきものです。
そのためには、リードの質や動きに関する振り返りを“定例化”する仕組みが有効です。
営業巻き込み型のリード会議、どう設計する?
たとえば月1回などの頻度で、営業とマーケの双方が出席する「リード定例会議」を設けている企業も増えています。
この会議で話すべきテーマの例:
- 「今月マーケから営業に渡したリードの傾向は?」
- 「商談化したリードの共通点は?」
- 「営業が“動きやすい”と思ったリードの特徴は?」
- 「次月以降の育成・提供方針のすり合わせ」
こうしたテーマを軸に議論を重ねることで、
形式的な報告会ではなく、“使える定義”を育てる場として機能します。
また、マーケティングが営業の声を拾うだけでなく、
営業自身も「自分たちの受注率を上げるために、定義と基準を育てる」という主体的な立場になれる点もポイントです。
さらに一歩踏み込んだ企業では、
以下のような工夫も行っています:
- SalesforceやHubSpotなどのCRM上に「MQL到達ログ」を記録
- 営業がSQL判断した理由をコメント入力
- マーケと営業のKPIを“セットで”ダッシュボード表示
こうした仕組みがあることで、主観ではなく“見える化されたフィードバック”として定義を磨いていくことができます。
BtoBマーケティングにおけるリード活用とは、単なるリード獲得やナーチャリング施策にとどまりません。
「自社にとっての“良いリード”とは何か?」を継続的に問い続けるカルチャーがあるかどうかで、その成果は大きく変わってきます
おわりに:連携設計にお悩みの方へ
「リードの定義は共有できたけれど、現場でうまく運用されない」
「営業とマーケの分担やKPI設計をどう整えるべきか悩んでいる」
──そんな方には、BtoB連携設計に特化した無料相談サービス『Markebuddy』の活用をおすすめします。
現場課題を一緒に壁打ちしながら、
自社にフィットした「リード活用プロセス」の整理をお手伝いします。
営業とマーケの分断を乗り越え、リードを売上に変えるために。
今日から一歩ずつ、仕組みを整えていきましょう。
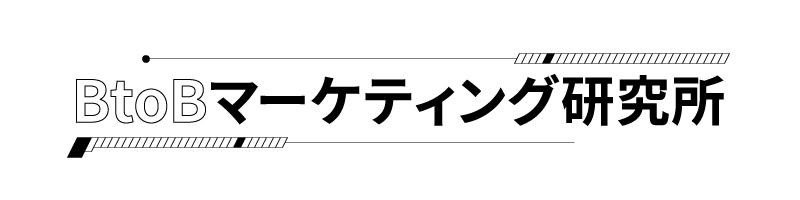
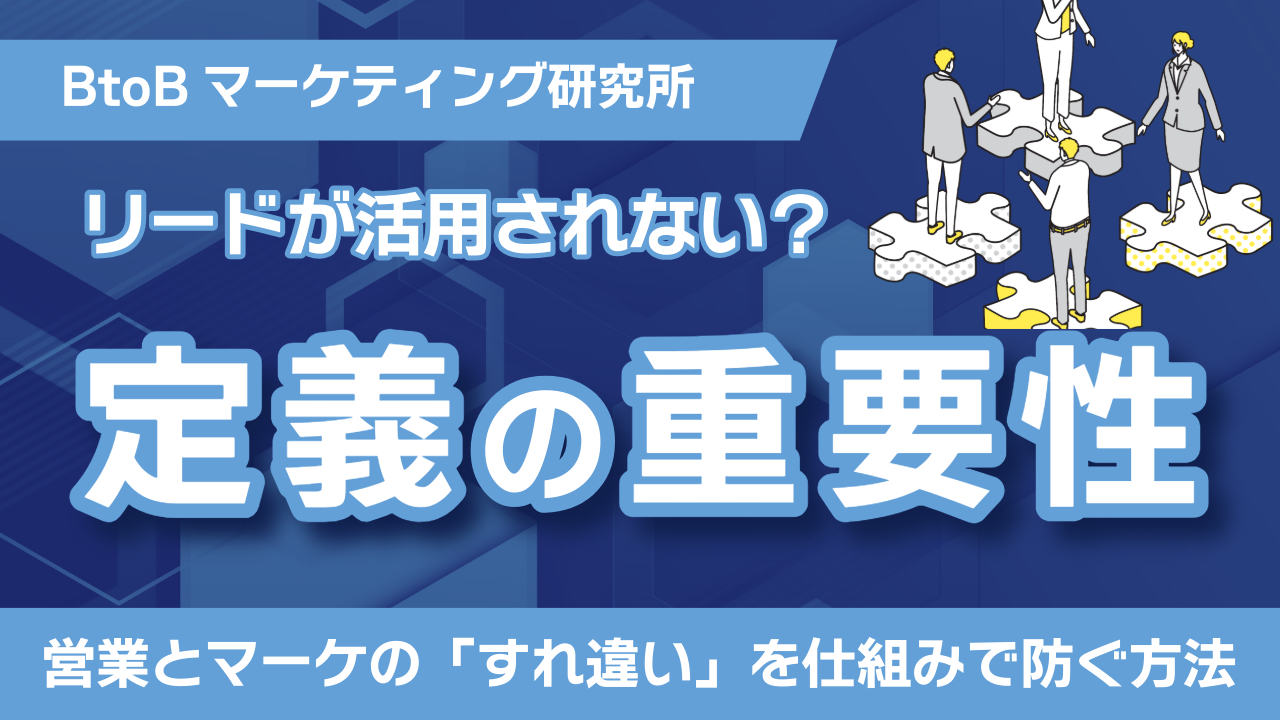


コメント