準備は完璧だったのに…展示会で成果が出ない理由とは?
「準備=成功」ではない現場のリアル
展示会の出展準備を完璧に整えたはずなのに、終わってみると「思ったほどリードが集まらなかった」「商談化にはつながらなかった」と感じたことはありませんか?
パンフレットも作り込んだ。ブースの装飾も目を引く。説明員のシフトも万全。にもかかわらず、成果が出ない──そんな“モヤモヤ”を抱える企業は少なくありません。
その背景には、「準備=成功」という認識のズレがあると考えられます。もちろん、事前準備は成果に直結する重要な工程です。ただし、それは“スタートライン”にすぎません。展示会の成否は、当日の“現場”での動き方によって大きく左右されるのです。
マーケティングや営業の現場では、どうしても「展示会は集客やブランディングの場」と捉えがちです。しかし、来場者と直接会話ができるこの貴重な機会は、営業活動の延長線上にあるべき現場です。準備段階での完璧さよりも、“当日どう動くか”の方が成果に直結する──これが、成果を出す企業の共通認識です。
成果を分けるのは“当日の動き方”
では、成果を出せる企業と、出せない企業を分ける最大の要因は何なのでしょうか?
その答えのひとつが、「現場のオペレーション」にあります。
展示会では、来場者の滞在時間は1ブースあたり平均2〜3分といわれています(※展示会主催各社の来場者調査より)。そのわずかな時間で、いかに印象を残し、興味喚起し、次のアクションにつなげるか──ここに、“現場力”の差が如実に表れます。
たとえば、同じ業種・同じ規模のブースでも、「声かけの第一声が違う」「立ち位置や視線の使い方が違う」「その場でリードの温度を把握している」など、微細な違いが蓄積して結果に大きな差を生むことがあります。
実際に、あるBtoB企業では、展示会での声かけや対応の仕方を一新しただけで、前年の倍以上の商談アポイントを獲得できたというケースもあります。しかも、事前準備はほぼ同じ。つまり、“当日の動き方が変わったこと”が成果の違いを生んだのです。
【参考リンク】
展示会って何すればいいの?若手マーケ担当の“当日ミッション”完全ガイド
https://btobmarketinglab.com/2025/04/14/exhibition-must-do/これだけ見ればOK!展示会担当者のための準備&当日運営マニュアル
https://btobmarketinglab.com/2025/04/14/tenjikai-todo-manual/
成果を出す企業に共通する「3つの現場アクション」
展示会で成果を出している企業に共通しているのは、「来場者との1分1秒を無駄にしない」動き方です。
準備をいくら万全にしても、それを“現場でどう活かすか”がカギ。ここでは、成果を上げている企業が実践している3つの具体的な行動をご紹介します。
1. 声かけの質が高い|一言目に“意味”がある
まず最も成果に直結するのが、「声かけの一言目」です。
来場者に立ち止まってもらえるかどうかは、この“一言”でほぼ決まるといっても過言ではありません。
成果を出す企業では、「○○にお困りの企業様ですか?」や「○○業界向けに特化した○○ソリューションです」など、“来場者の関心・課題に直結する言葉を冒頭に置いています。
逆に、成果が出ないパターンでは、「こんにちは」「何かお探しですか?」といった汎用的な挨拶に留まってしまうケースが多く見られます。これでは、情報感度が高い来場者ほどスルーしてしまう可能性が高まります。
▶現場で使える声かけ例(製造業向けソリューションの場合)
- NG例:「こんにちは〜、ご覧ください!」
- OK例:「製造現場の○○でお困りではないですか?」
関連記事:「声をかけるのが苦手な人でも大丈夫!展示会で自然に話せるトークスクリプト」
https://btobmarketinglab.com/2025/04/14/exhibition-talk/
2. チーム連携が取れている|誰が何をするか明確
ブースに立つ人数が多くても、それぞれの役割が曖昧だと逆効果です。
成果を出す企業は、展示会当日の動きを「事前にシナリオ化」しています。
たとえば──
- 誰が声かけを担当するか
- 会話が始まったら誰がバトンを受けるか
- 深い相談が入ったら誰に繋ぐか
- 記録・スコア付けは誰が行うか
こうした動きを“秒単位で可視化”しておくことで、現場での迷いや被りがなくなり、来場者対応の精度が上がります。
特に、営業・マーケが混在するチームでは、「フォロー判断」を誰がするかを曖昧にしてしまうと、ホットなリードを逃す結果にもなりかねません。
展示会はマーケティングの仕事…と思われがちですが、売上に近い“営業活動の現場”として設計することが重要です。商談化のゴールから逆算して、誰が・何を・どこまで対応すべきかをチーム全体で共有しておくこと。それが、成果につながる展示会の第一歩です。
3. その場でリードの“温度”を記録している|即時スコアリング
成果を出す企業が展示会で必ず行っているのが、「その場での温度感の記録(スコアリング)」です。
たとえば──
- 名刺交換時に「興味度・導入時期・課題感」などを5段階で記録
- 来場者の関心カテゴリをタグで選択(例:製品A/製品B/価格面など)
- 会話後すぐに、商談化しやすさをチェック項目で簡易評価
こうした即時記録があることで、展示会後のフォロー精度が圧倒的に変わります。成果が出ない企業では、名刺だけで判断して一律メルマガを配信して終わってしまうケースが多く、結果として“商談化できるリード”を取り逃がしているのです。
▶現場で使えるツール例:
- Googleフォームでスコアリングシートを用意(スマホ入力用)
- QR付きリードカードを配布し、スキャン後に温度記録
当日オペレーションを改善するためのチェックポイント
展示会での「動き方」を改善するには、ただ気合いや人数を増やすだけでは成果につながりません。
重要なのは、“どこを見るか・どこを変えるか”という視点を持ち、ブース運営を最適化していくこと。
このセクションでは、現場でのパフォーマンスを底上げするために、実践的な3つの観点を解説します。
現場で役立つ立ち位置と動線の考え方
展示会ブースでは、「誰がどこに立つか」で来場者の反応が大きく変わります。
ありがちなNG例は、全員がブース内に引っ込んでしまい、来場者が入りづらくなってしまうパターンです。
また、前を通った人に対して背中を向けているなど、無意識のうちに“声をかけにくい空気”を作ってしまうケースもあります。
成果を出す企業は、視線・導線・立ち位置の“戦略的配置”をしています。
▶動線設計の実例:
- 一人はブース前に立ち、アイキャッチと声かけを担当(フロント担当)
- 一人は中央で会話対応(製品紹介、接客担当)
- 一人は奥側で資料渡しやスコア記録などのサポート(事務作業担当)
来場者の流れを「入りやすく、出やすい」ものにすることで、滞在時間が伸び、会話が始まりやすくなります。
営業・マーケの“その場での連携”はどう作る?
展示会では、マーケティング部門と営業部門が混在して対応する場面が多くあります。
しかし、ここに「誰が主導権を握るか」「どうバトンを渡すか」の設計がないと、せっかくのホットリードがこぼれてしまう原因になります。
成果を出している企業は、事前に“即興的な動き”を想定して、柔軟な対応ルールを整備しています。
▶連携の鉄則:
- 課題ヒアリングの途中で「これは案件化できそう」と判断したら即座に営業へパス
- 営業が話し中のときはマーケが仮受付し、後で個別対応
- CRMやスプレッドシートで「現場での対応履歴」をリアルタイム共有
こうした柔軟な“即連携”ができるチームこそが、リードを逃さないのです。
声かけ〜フォローの「一貫性」を意識した運営術
展示会の現場では、“その場の対応”がしっかりしていても、展示会後のフォローで一貫性がないと、来場者の関心は一気に冷めてしまいます。
成果を出す企業は、展示会当日の対応内容が、そのままフォロー施策に連動するような設計をしています。
▶一貫性ある運営の工夫例:
- 初回の声かけ文言と、フォローメールの件名・導入文を揃える
- 配布資料とWebフォームの内容を連動させておく
- 「会話中の関心事」に沿った資料を自動で送るフォローシステムを用意
つまり、“展示会は単体イベントではなく、商談設計の一部”という位置づけで運営しているのです。
まとめ|成果を出す展示会チームは“現場での動き”が違う
展示会で成果が出るかどうかは、「準備の完璧さ」だけで決まりません。
むしろ、当日の現場でどう動くかが、商談・リード獲得に直結します。
本記事では、成果を出す企業が共通して実践している“3つの現場アクション”と、今すぐチェックできる改善ポイントを紹介してきました。
改めてポイントを振り返ると──
- 第一声に「意味」を込めた声かけで、来場者の関心を一瞬で掴む
- 明確な役割分担とチーム連携で、商談の取りこぼしを防ぐ
- 即時スコアリングでリードの“温度”を可視化し、後の施策につなげる
さらに、立ち位置・動線の工夫や、営業とマーケの連携設計、フォローとの一貫性までを含めて設計することで、展示会の現場は“単なる出展”から“営業成果をつくる場”へと進化します。
現場でのちょっとした工夫が、商談数・成約率を左右します。
もし「自社も動き方を見直したい」と感じた方は、以下の無料リソースを活用してみてください。
メルマガ登録
展示会ノウハウが届くメルマガを配信中!
登録はこちら
Markebuddy無料相談
「展示会の成果、もっと上げたい」方へ。現場改善から商談設計まで支援いたします。
詳しく見る
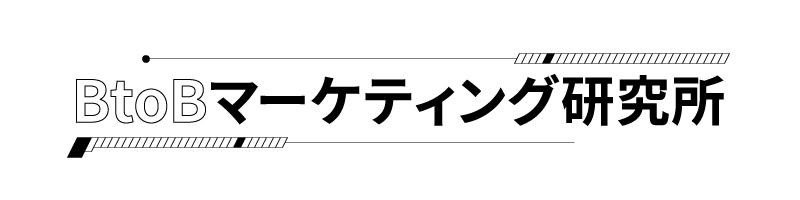

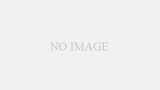

コメント