展示会が“属人化”しやすい3つの理由
展示会は、出展すること自体に加えて、ブース設営、来場者対応、資料準備、事後フォローなど多岐にわたる業務が発生します。にもかかわらず、実際の現場では「気づいたら若手一人がすべて抱えていた」という状況も少なくありません。
なぜ、展示会はここまで属人化しやすいのでしょうか。その背景には、組織やチーム運営の構造的な要因があります。ここでは、特に起こりがちな3つのケースを見ていきましょう。
「あの人がやってるから」と任せっぱなしになる
展示会準備は突発的な業務も多く、結果的に「慣れている人」や「過去に担当した人」が継続的に任されがちです。チーム内で「〇〇さんに任せておけば大丈夫」という空気が生まれると、自然とその人中心で業務が進行してしまいます。
特に中小企業では「人数も少ないし、慣れている人にやってもらった方が早い」という判断が無意識にされがちですが、これはリスクでもあります。担当者が休んだり異動した際に、誰も内容が把握できていないという事態になりかねません。
情報共有が不十分で、他メンバーが把握できない
属人化が進行するもう一つの理由は、「何をやっているのかが他の人に見えない」状態になっていることです。
口頭のやり取りや、個人のPC上にだけある資料、バラバラのメール連絡など、情報が分散していると、他のメンバーは進捗や課題を把握できません。
結果として、いざ支援が必要なときに「どこまで終わってる?」「何を手伝えばいい?」とゼロから聞き直すことになり、かえって非効率になってしまいます。
社内での報連相(報告・連絡・相談)がされていないわけではなくても、「誰にでもわかる形式で」「誰でもアクセスできる形で」情報を共有しておくことがされていないことが多いのです。
準備物や進行の全体像が見えない
展示会準備は、数週間から数か月にわたってさまざまなタスクが並行して進みます。にもかかわらず、全体像が一枚の絵として可視化されていないことが、属人化を加速させる要因になります。
たとえば、「パンフレットは誰が作る?」「会場とのやりとりは誰が?」といった業務の役割分担が曖昧なままだと、どうしても一部の人が“なんとなく”対応してしまい、結果的に一人に負担が集中してしまうのです。
また、展示会の直前や当日に「あれ、誰がこの備品手配してた?」といったトラブルも、全体管理の不足から発生しがちです。こうした準備全体の可視化ができていないことが、属人化の根本原因のひとつといえるでしょう。
属人化を防ぐために必要な「仕組み」と「共有ルール」
展示会準備をチームで進めるうえで、個人に依存しない体制づくりは欠かせません。そのためには、場当たり的に対応するのではなく、仕組みとして「誰でも動ける」状態をつくることが重要です。
ここでは、属人化を防ぐために中小企業でも取り入れやすい3つの基本策をご紹介します。
業務を可視化する:ガントチャート or タスク管理表の活用
まず取り組みたいのが「見える化」です。
展示会準備は、「誰が・いつまでに・何をやるか」が明確でなければチームで動けません。
そのためにおすすめなのが、ガントチャートやタスク管理表の活用です。ExcelやGoogleスプレッドシートでも簡単に作成でき、下記のような形式で全体の進捗と担当者を一元管理できます。
- 各タスクの内容(例:ブース設営、チラシ制作、備品手配など)
- 担当者(複数名の共同担当でも可)
- 期限とステータス(未着手/進行中/完了)
- 優先度や関連メモ
最近では、NotionやBacklog、Trelloなどのタスク管理ツールを活用する企業も増えています。
クラウドで管理すれば、在宅勤務中でもリアルタイムで状況を確認でき、属人化リスクを大きく軽減できます。
総務省の「令和4年通信利用動向調査」によると、中小企業でも業務の見える化を目的にタスク・プロジェクト管理ツールの導入が進んでいると報告されています。
出典リンク(総務省)
チーム全員で“目的”と“成功条件”を共有する
次に大切なのが、準備の“目的”を全員で共有することです。
属人化の背景には、「担当者以外が展示会の意義やゴールを理解していない」状態があります。
たとえば、「この展示会では◯件のリードを獲得したい」「ターゲットは〇〇業界の意思決定者」など、目的・KPI・来場者像をチームで明確にし、全体ミーティングなどで共有しましょう。
これにより、「ただの出展作業」ではなく、営業・広報・総務など各部門が自分ごととして動ける体制が生まれます。
🔗関連記事:
展示会で「何が成功?」と聞かれて困らないための、評価軸の作り方
展示会出展のKPIとは?展示会におけるKPI設定の重要性
「誰でも回せる」業務設計とドキュメント化
属人化を防ぐ決定打となるのが、「引き継げる状態」の作成です。
準備業務のフローや判断基準を、ドキュメントとして残しておくことで、誰が見ても次に何をすべきか分かるようになります。
たとえば、以下のようなフォーマットを用意することで、対応の抜け漏れや混乱を減らすことができます。
- 展示会準備マニュアル(チェックリスト+工程ガイド)
- 過去の展示会報告書(成果・反省点・使用資料など)
- 各担当者向けの役割ガイドライン
最初は手間に感じるかもしれませんが、2回目以降の準備効率が大きく改善され、「この資料を見れば動ける」状態が継続的に作られます。
チームで動ける展示会準備の進め方
展示会準備をチームで進めるには、「仕組み」だけでなく日々の進め方や他部門との連携がカギになります。
特に、最初の動き出しや当日に向けた役割整理の段階で、属人化を防ぐ布石を打っておくことが大切です。
ここでは、実践的にチームで動くための3つのステップをご紹介します。
キックオフミーティングの進め方と共有事項
準備を始める際に必ず行いたいのがキックオフミーティングです。
ここで目的や役割を共有することで、初期段階からチームでの連携が生まれやすくなります。
キックオフで確認すべき基本項目は以下のとおりです:
- 展示会出展の目的(例:新規リード獲得、製品認知拡大など)
- ターゲット来場者のペルソナ
- 成功指標(例:名刺◯枚、商談化率など)
- 各部門・メンバーの役割と期待される貢献
- 全体スケジュールとタスク分担(前セクションの可視化表と連動)
また、議事録を残して共有ドライブなどで見える化しておくことで、「聞いていない」「知らなかった」といった属人リスクも回避できます。
営業・総務・制作との連携ポイント
展示会準備はマーケティング部門だけで完結するものではありません。
成果を最大化するには、営業・総務・制作などの関係部門との密な連携が不可欠です。
各部門との連携ポイントは以下のようになります:
- 営業部門:顧客ペルソナの設定、ブースでの対応、リード管理、事後フォロー
- 総務部門:備品調達、出張手配、ブース施工業者とのやりとり
- 制作チーム:パネル・チラシなどクリエイティブの作成、納品管理
それぞれが「自分のタスク」ではなく、「チームでの成功」の一部と捉えられるように、共有ミーティングや進捗報告の場を定期的に設けることが効果的です。
「当日対応表」と「役割マニュアル」の作り方
展示会当日はトラブルもつきもの。だからこそ、事前の役割分担と対応フローの整理が重要です。
属人化を避けるためにも、「当日何をするか」が誰でも分かるようにしておきましょう。
おすすめなのは、以下のようなフォーマットでまとめた「当日対応表」と「役割マニュアル」の作成です。
| 時間帯 | 担当者 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9:00〜 | Aさん | ブース設営チェック | 業者到着確認含む |
| 10:00〜 | Bさん | パンフレット配布 | 補充対応含む |
| 随時 | 全員 | 来場者対応 → 名刺回収 → 管理表入力 | 名刺データは即日チーム共有 |
さらに、急な欠席などに備えて代替要員の割り当ても明示しておくと、当日の混乱を防げます。
このような資料を事前に配布・共有し、説明会を行っておくこともポイントです。
事例に学ぶ!属人化排除に成功した展示会チームの工夫
属人化のリスクを感じながらも、「具体的にどう変えればいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで参考になるのが、他社がどのように属人化を防ぎ、チームでの展示会運営を実現したかという実例です。
ここでは、2社の成功事例を紹介します。
例① 若手1名 → 営業巻き込み型に転換した製造業
ある中堅製造業では、毎年の展示会準備を20代の若手マーケティング担当が1人で担っていました。
過去の資料をもとに、ひとりで手配からパネル制作、営業部門との連絡までこなしていたため、他メンバーは全体像を把握できていない状態でした。
転機となったのは、展示会当日にその担当者が急な体調不良で不在になったこと。誰も準備の詳細を把握しておらず、大きな混乱が生じました。
これを機に、次回の展示会では営業部門との共同プロジェクト体制へとシフト。以下のような工夫を行いました。
- キックオフ時点で営業部門からも複数名をアサイン
- リード獲得後のフォロー体制までを一体で設計
- タスク進行をGoogleスプレッドシートで全体共有
- 来場者対応マニュアルを営業視点で再設計
結果として、営業側も「展示会は自分たちの成果に直結する」と実感を持ち、当日の参加率・リード管理の精度も大きく改善。
マーケ担当も業務が分散され、準備時間の短縮とミスの減少につながりました。
例② Excel進行 → Notion共有で全員参加に変えたIT企業
BtoB向けSaaSを展開するIT企業では、展示会準備をExcelベースで管理していたものの、資料が個人PCに保存されており、他メンバーが状況を把握できないという課題がありました。
準備タスクの進捗も不明瞭で、「何を手伝えばいいのか分からない」と感じる社員が多く、マーケ担当者の負担が膨らむ一方でした。
そこで導入されたのが、Notionを活用したタスクと資料の一元管理です。導入により、以下のような変化がありました。
- ガントチャート形式で全体スケジュールを共有
- チェックリスト形式で各人の役割・期日を明確化
- 進捗コメントを残すことで離れていても情報が可視化
- 会場MAP、対応マニュアル、過去の成果もNotion上に集約
この結果、「誰かの頭の中にしかない情報」がゼロになり、他部門からの支援も得やすくなったそうです。
属人化の不安が消えたことで、展示会準備が「個人の負担」から「チームのプロジェクト」に変化しました。
まとめ|展示会の成果は「準備の透明性」と「チーム運営」で決まる
展示会準備は、つい特定の担当者に任せきりになりがちですが、それでは成果を最大化することは難しくなります。
属人化を防ぎ、「誰でも動ける」体制をつくることこそが、展示会成功への第一歩です。
そのためには、
- 全体スケジュールやタスクを“見える化”すること
- チーム全体で“目的”と“成功条件”を共有すること
- 情報や対応をマニュアル化し、引き継ぎ可能な状態をつくること
といった基本的な取り組みから始めるのが効果的です。
実際にご紹介したように、Notionなどのツールを活用したり、営業部門を巻き込んだ体制づくりを行えば、展示会は“個人の仕事”から“組織のプロジェクト”へと進化します。
Markebuddy無料相談:展示会準備の属人化、解消しませんか?
もし「自社もつい若手に任せてしまっている」「チームで動きたいが仕組みがない」と感じている方は、Markebuddyの無料相談をご活用ください。
展示会の計画から進行管理、チーム設計まで、専門スタッフが貴社の課題に合わせてサポートします。
👉 無料相談はこちら
メルマガ登録:展示会ノウハウを継続的にキャッチ
また、展示会のKPI設計、チェックリスト、事後フォローの設計など、実務に役立つノウハウを毎月配信しているメルマガも好評です。
興味のある方は、ぜひ下記からご登録ください。
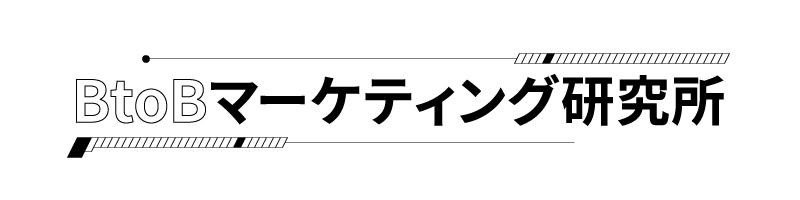

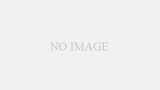
コメント