展示会の成果、「リード数」だけで語っていませんか?
上司や営業が求める「成果」と、マーケ視点のズレ
展示会の後、必ずといっていいほど上司や営業から投げかけられるのが「で、成果どうだったの?」という質問です。
このとき、多くの若手マーケティング担当者が真っ先に挙げるのが「リード数」ではないでしょうか?
たしかに、名刺の数やスキャン数は数字として残しやすく、報告しやすい指標です。
ですが、「リード数が多ければ成功か?」という問いには、明確に「Yes」とは言い切れません。
なぜなら、営業側が求めているのは「案件化する見込みの高いリード」であり、マーケティング側が集めた数とは評価の視点が異なるからです。
この視点のギャップが埋まらないと、展示会の成果は評価されず、「また数集めただけだね」と言われてしまうこともあります。
つまり、「何をもって成功とするか?」を関係者で共有しておかないと、せっかくの展示会施策も意味を持ちづらくなってしまいます。
展示会の評価は、最終的に営業活動にどれだけ貢献したかという視点で見ていくことが欠かせません。
そもそも展示会の目的は1つではない
ここで改めて考えたいのが、「展示会の目的はそもそも何だったのか?」という点です。
展示会と聞くと、「新規リード獲得」だけが目的と思われがちですが、実際には以下のような多様な目的があります。
- ブランド認知・露出の向上
- 既存顧客・パートナーとの接点強化
- 新製品・サービスの紹介と市場の反応収集
- 営業活動のサポート(商談発生・検討フォロー)
こうした目的ごとに、「成果」の定義や、評価すべき指標(KPI)は変わります。
にもかかわらず、「とりあえず名刺を何枚集めたか」で成功を語ってしまうと、本来達成すべき目的がぼやけてしまうのです。
そのため、展示会を振り返る際には、「何のために出展したのか?」という目的と、「何が達成できたのか?」という成果をセットで見ていく必要があります。
「展示会の評価軸」はこう考える!3ステップで設計する方法
展示会の「成功」を語るには、そもそも何を基準にするのか、その評価軸(=判断のモノサシ)を明確にする必要があります。
とはいえ、初めて展示会を担当する人にとっては、「どこから手をつければいいかわからない…」というのが本音ではないでしょうか?
ここでは、展示会の評価軸をつくるための3ステップを紹介します。
この順番で考えることで、目的に沿ったKPI設計と振り返りがグッとやりやすくなります。
1. 目的を整理する(認知/獲得/関係構築 など)
まずは「なぜ出展するのか?」という目的を言語化することが何より大事です。
展示会には複数の目的がありますが、主に以下の3つのどれに当てはまるかを整理しましょう。
- 認知目的:まだ接点のないターゲット層に自社を知ってもらう
- リード獲得目的:見込み顧客との新たな接点をつくる
- 関係構築目的:既存顧客・パートナーとの関係を深める
ここが曖昧なまま進めると、展示会後の評価軸もブレてしまい、「成功だったのかどうか」が判断できなくなってしまいます。
目的を明確にするには、出展前に営業やマネジメント層とのすり合わせが重要です。
「今回の展示会は何をゴールにするのか?」を事前に共有しておくことで、成果の認識ズレも防げます。
2. 成果を可視化できるKPIに落とし込む
目的を明確にしたら、次は「達成度をどう測るか」を考えましょう。
ここで重要なのが、成果を“見える化”するKPI(重要業績評価指標)です。
たとえば、目的が「リード獲得」なら、以下のような指標が候補になります
- スキャンした名刺・QRコードの件数
- アンケート回答数や関心度のスコア
- 商談につながる見込みリード数
一方、目的が「認知拡大」であれば、
- 資料の持ち帰り数
- ブース訪問者との会話件数
- SNS投稿やWebトラフィックの増加
などが指標になります。
ここで大事なのは、「現場で集計可能な数字」であることです。
あとで振り返るときに困らないよう、取得方法も事前に決めておきましょう。
3. 振り返りのための“記録・記述”をセットで残す
意外と見落とされがちなのが、「数字だけでは伝えきれないこと」の記録です。
KPIはあくまで定量的な成果の一部。これに加えて、“現場の声”や“気づき”などの定性的な情報も、しっかり残しておくことが大切です。
たとえば
- 来場者からよく聞かれた質問内容
- ターゲット層の反応や印象的なエピソード
- 営業が「これは良い感触」と感じた具体的な理由
こうした情報は、次回出展時の改善や、展示会後の営業活動にも活かされます。
記録の方法としては、出展メンバーに「簡易な報告フォーマット」を渡しておき、終了直後にサッと書いてもらうのがオススメです。
日本能率協会「展示会出展効果に関する調査(2022年)」によると、出展目的を明確にしている企業は、出展成果を「満足」と評価する割合がそうでない企業の約2倍にのぼるという結果も。
(参考:https://www.jma.or.jp/exhibition)
目的別に見る!展示会評価KPIの具体例
ここからは、「目的に応じて、どんなKPIを設定すべきか?」をより具体的に見ていきましょう。
目的ごとに評価すべきポイントは異なるため、自社の出展目的と照らし合わせながら読み進めてみてください。
ブランド認知目的の場合|名刺数/来場者との会話数/資料持ち帰り数
新規市場へのアプローチや、新ブランド・新サービスのローンチなど、「まずは知ってもらうこと」を重視する場合には、接触機会の量と質を測る指標を設定します。
以下のようなKPIが適しています
- 名刺交換数/QRスキャン数
- 来場者との会話数(1分以上など)
- 資料持ち帰り数/配布率
- SNSやWebサイト流入数の変化
また、来場者の属性(業種・職種・役職など)を記録できると、ターゲット層への到達度も評価しやすくなります。
リード獲得目的の場合|商談化見込み/アンケートからの関心度スコア
「商談のタネを集めたい」目的であれば、単なる名刺枚数よりも“見込み度の高い接点”をどれだけ作れたかが重要です。
この目的に合うKPI例は
- アンケート回答数/関心度スコア
- 製品デモ実施件数
- その場で商談予約を獲得できた件数
- 来場者が抱えている課題の記録数
商談化見込みやフォロー率といった営業接続後の数値をKPIに含めておくと、マーケ施策の価値が営業部門に伝わりやすくなります。
営業連携・既存接点活性化の場合|面談数/再接触発生件数
中には、「既存顧客・既存リードとの接点強化」を目的とした出展もあります。
こうした場合は、既存接点との“再接触”や“関係性の深化”にフォーカスした指標を設定しましょう。
たとえば
- 事前アポイント面談数
- 既存顧客との会話件数/名刺交換数
- 再接触発生件数(展示会後の再商談など)
- ナーチャリング接触率(メール開封・セミナー参加など)
中小企業基盤整備機構「展示会を活用した販路開拓支援に関する調査(2021)」によると、出展企業の約3割が「既存顧客との関係維持・再活性化」を主要目的に掲げており、新規獲得一辺倒ではない活用が進んでいることがわかります。
(参考:https://www.smrj.go.jp)
評価を次につなげるために|報告と改善のすすめ方
展示会は出展して終わりではありません。
むしろ重要なのは、「成果をどう報告し、どう改善に活かすか」というアフターの動きです。
展示会施策を単発に終わらせず、次回に活かせるサイクルを回すためには、報告の設計と改善提案の伝え方がカギを握ります。
報告資料の基本構成と伝え方
展示会後、上司や営業に報告する際には、以下の構成を押さえておくとスムーズです。
- 展示会概要
- 日時/場所/対象展示会の説明
- 出展目的の再確認
- 目的に対して、どんなKPIを設定したか
- 定量成果(KPI)
- 名刺獲得数、面談数、関心度スコアなど
- 定性成果(現場での気づき)
- 来場者の声/よく聞かれた質問/反応が良かったポイントなど
- 営業視点での評価(あれば)
- 展示会後の商談数やフォロー件数など
- 次回への示唆
- 何がうまくいったか、改善点は何か
特に、「目的→KPI→成果→改善」のストーリーがつながっていると、説得力のある報告になります。
ポイントは、「数値だけでなく、現場のリアルな声も伝えること」。
「こういう質問が多かった=市場の関心が高い」など、営業が次に活かせるヒントが詰まっています。
「次回改善案」の出し方と関係者巻き込みのコツ
営業や製報告の最後に忘れてはいけないのが、「次はどうするか?」という改善提案です。
ここで大切なのは、「マーケだけで考えず、関係者の声を拾っておく」こと。
展示会はチーム戦です。営業、製品担当、現場スタッフなど、関わったメンバーそれぞれに視点があります。
たとえば
- 営業からのフィードバック:「もう少し製品別のチラシが欲しかった」「◯◯業界の反応が良かった」
- 製品担当からの意見:「質問が多かったテーマを資料に反映したい」
- 現場スタッフの気づき:「動線が悪くて回遊されにくかった」など
こうした声を集めて、「次回こう変えてみたい」と具体的に提案すると、組織内での納得感と期待値が高まります。
また、改善提案は次の出展判断にも影響するため、単なる“振り返り”で終わらず、次のアクションを動かす報告にするのが理想です。
展示会の準備〜当日の動き方を知りたい方は、
「展示会って何すればいいの?若手マーケ担当の”当日ミッション”完全ガイド」もあわせてご覧ください。
まとめ|展示会は「目的×評価軸」で初めて成果が見える
展示会の成果は、「名刺を何枚集めたか」だけでは語れません。
本当に大切なのは、その展示会が何のための出展で、どんな成果を得るべきだったのかという「目的」と「評価軸」がセットであることです。
特に若手マーケティング担当者にとっては、「上司や営業にどう説明すればいいかわからない」という不安がつきもの。
ですが、目的を言語化し、それに沿った指標を選ぶことで、展示会の成果はちゃんと伝えられるようになります。
そして何より、展示会の評価は“現場で終わり”ではなく、営業活動への貢献や、次回施策への改善提案へとつなげていくことが、マーケティング担当としての腕の見せどころです。
📩 展示会ノウハウをもっと知りたい方へ
実践的なノウハウが届くメルマガを配信中です。登録はこちらから。
🟢 Markebuddy無料相談はこちら
展示会の「目的整理とKPI設計」に悩んだら、BtoB専門のプロがサポートします。
▶︎無料相談を申し込む
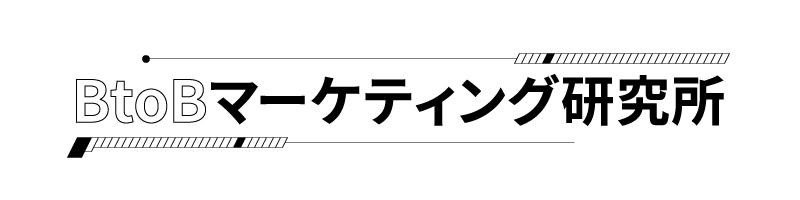

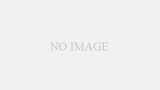
コメント