展示会当日、若手マーケ担当が抱える悩みとは?
はじめて展示会の現場に立つと、「で、自分は何をすればいいんだろう?」と戸惑うことが多いものです。準備期間中は「資料を印刷した」「パネルを手配した」とタスクが明確でも、当日は“現場でどう動けばいいか”のマニュアルが意外とない──そんな状況に直面する担当者も少なくありません。
展示会の規模と注目度は?統計から見る“リアルな現場”
展示会はBtoBマーケティングにおいて今なお重要な施策です。実際、日本展示会協会の調査(2019年)によれば、1年間で開催された展示会は603件、総来場者数は約749万人。そのうち93.7%がBtoB展示会という結果が出ています。
また、出展社の約19%が海外企業であることからも、展示会はグローバルな情報交換・商談の場として活用されていることがわかります(出典:日本展示会協会)。
このように多くの企業が出展し、競合やパートナーとも直接接点を持てる貴重な機会である反面、「どこから手をつければいいのか分からない…」と戸惑う担当者も多いのが実情です。
何をすればいいかわからない
「名刺を取ればいいんですよね?」「立ってるだけでいいですか?」──こんな風に、当日の動きがあいまいなまま現場に入ると、自信を持って立ち回れず、ブースの“空気”に飲まれてしまうことも。
特に若手担当者は、「他のメンバーの動きについていくのがやっとだった…」というケースもよく聞きます。
営業とどう動けばいいのか不明
展示会はマーケと営業が“同じ空間”で動く数少ない場ですが、「誰が声をかけて、誰が商談につなげるのか?」という役割の境界線が見えにくいこともあります。
うまく連携できれば成果につながりますが、連携があいまいだとチャンスを逃してしまうかもしれません。
成果をどう定義すればいいか迷う
「名刺◯枚集まりました!」だけで本当にOKなのか?
上司から「で、どうだったの?」と聞かれて答えに詰まった…という経験がある方も多いはずです。
展示会の成果は名刺の数だけではなく、“次につながる情報”がどれだけ取れたかも重要なポイントです。
展示会“当日の流れ”と担当者のミッション
会場到着〜開始前にやるべきこと
展示会の勝負は、始まる前から始まっていると言っても過言ではありません。若手マーケ担当としては、以下のようなチェックポイントを押さえておくと安心です。
- 会場入りのタイミングは、開始の1〜1.5時間前が目安
- ブースの最終チェック(パネルのズレ、資料の補充、デモ機の起動など)
- 営業メンバーとの事前すり合わせ(声かけのトーン、役割分担)
- 名刺管理やリード記録の運用確認(MA/SFAとの連携がある場合は動作チェック)
また、来場者導線の確認や、ブース近辺の出展社の様子を見ておくのも有効です。「この配置だと、左側からの人の流れが多そうだな」といった気づきが、ブース前での立ち位置や声かけに活きてきます。
展示時間中の動き方(立ち位置・声かけ)
展示会中の立ち回りで差がつくのは、“ただ立っている”のではなく、目的意識をもって動けているかどうかです。
- 来場者が立ち止まりやすい立ち位置を取る(ブースのやや前方・左右を意識)
- 営業とバッティングしない声かけの仕方(「こんにちは、お立ち寄りありがとうございます!」など、自然なアイスブレイク)
- リードの温度感を見極めて、営業パス or 情報取得の判断をする
若手マーケとしては、営業のサポート役に徹しつつ、「どういう人が来場していて、何に興味を持っているか?」という情報を拾うことが大切です。
この情報は、後の分析やナーチャリング設計にも活かされます。
終了後にやるべき「すぐやる仕事」
展示会が終わってホッと一息…の前に、当日中にやっておくべき仕事があります。ここをやるかやらないかで、成果の質が大きく変わります。
- 集まった名刺やリード情報の一次分類(温度感・商談フェーズ・メモなど)
- 営業メンバーとその場でフィードバック共有(「あの方は受注の見込み高そう」「こんな質問が多かった」など)
- 来場者数や人気コンテンツなど、簡単なサマリーを残しておく
当日の熱量や肌感覚は、時間が経つほど薄れてしまうもの。だからこそ、「展示会当日が終わった瞬間」が、若手マーケの真価が問われるタイミングです。
現場で差がつく!意識すべき3つのポイント
営業との役割分担と連携
展示会はマーケティングと営業の“協業の場”です。
しかし現場でありがちなのが、「営業に任せればいいよね」と役割を曖昧にしてしまうパターン。
ここで大切なのは、お互いに“どこまでを誰がやるか”を事前に握っておくこと。たとえば:
- 初期対応はマーケ、詳細説明は営業
- アンケート取得はマーケが声がけしてサポート
- ホットリードの判定はその場で相談して分担
このように、共通認識を持っておくことで、現場での迷いを減らし、来場者にもスムーズな対応が可能になります。
ブース内の動線と滞在時間の最適化
実は、来場者がブースに「なんとなく立ち寄ったけど、すぐ離れた」というケースは非常に多いです。
そこでマーケ担当が気を配るべきは、ブース内の“動線”と“滞在時間”です。
- 資料やパネルの配置は、自然と中まで進みたくなる設計に
- 滞在時間が長くなりそうな場合は、サブ資料やデモ導線でフォロー
- 動線が混み合っていたら、立ち位置を変えて“滞在しやすさ”をサポート
こうした“気づきと小さな調整”を意識できると、結果として得られる名刺の質や商談機会の数にも差が出てきます。
「名刺数」だけで満足しないための記録術
展示会の成果は「名刺の数」だけでは測れません。
むしろ、“どういう温度感の人が、何に関心を持っていたか”という情報をどう記録できたかが重要になります。
おすすめは、以下のような簡易タグやコメントメモの運用です:
- A:商談化の可能性が高い(すぐ営業フォロー)
- B:興味関心あり(後日ナーチャリング対象)
- C:情報収集段階(定期的な接点づくりが必要)
加えて、「〇〇という課題に反応」「□□の事例に興味を示していた」といったメモを残しておくことで、次のマーケ施策にもつなげやすくなります。
失敗しないための事前準備と“共有ルール”
全員で「目的と評価指標」を共有する
展示会は単なる“名刺集め”ではなく、マーケティング施策のひとつとして成果を測るべき場です。
そのためには、関係者全員が「何のために出展するのか?」「成功の定義は?」を共通認識として持つことが不可欠です。
たとえば以下のような共有を事前にしておくと◎:
- 目的:新規リードの獲得/特定商材の認知向上/既存顧客との関係強化など
- 成果指標:名刺の数、特定ターゲット層の比率、商談化リード数 など
- 当日の役割分担とリード定義(営業パス or ナーチャリング対象)
こうした共通言語があれば、当日のブース対応にも判断軸ができ、営業・マーケが同じ方向で動けるようになります。
SFAやMAとの連携設計は当日にも影響する
展示会のリード獲得は、「名刺を集めて終わり」ではなく、その後のフォロー設計まで含めて“運用設計”として成立します。
そこで、以下のようなシステム連携の確認も、できるだけ展示会前に行っておくと安心です。
- 名刺情報の入力方法(手書き・OCR・MAフォーム連携など)
- MA(マーケティングオートメーション)やSFAとの連携有無
- リード情報の属性・関心項目をどう記録するかのルールづけ
- 当日、誰が・いつ・どのようにデータを処理・反映するかの役割決め
特に「入力ミスが多くて使えない」「リード判定が後手に回った」といった“翌日のバタつき”は、当日の設計不足が原因であることも多いです。
展示会の成果は、営業だけでなく、マーケとしても“数字で語れる状態”に持っていくことが求められます。そのためにも、システム・運用の連携は欠かせません。
まとめ|当日の行動が、展示会成果を左右する
展示会は、事前準備・ブース設営・リード管理など多くのタスクがありますが、最も成果に直結するのは“当日の動き方”です。
若手マーケ担当が現場でできることは、「ただ立って名刺を集める」だけではありません。
- 営業と連携しながら声かけを工夫する
- ブース内の動線や滞在時間を意識する
- 名刺の“質”を見極め、次につながる記録を残す
こうした細かな積み重ねが、「この展示会やってよかったね」と言える結果につながっていきます。
そしてもう一歩進めるなら、展示会の成果を営業貢献につなげる仕組み設計がカギになります。
運営の最適化だけでなく、その先の「リード活用」「SFA・MAとの連動」「受注までのナーチャリング設計」までを見据えて動けると、マーケとしての存在感もぐっと高まるはずです。
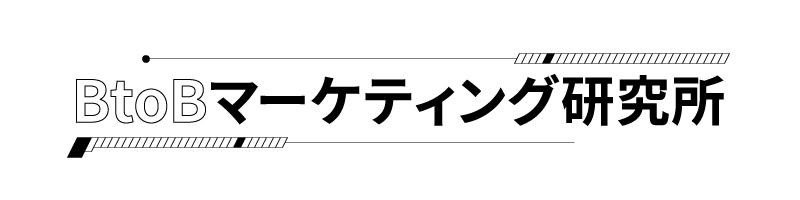


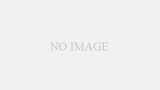
コメント